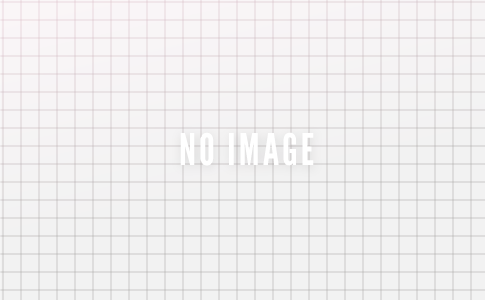新潟空港に向かう途中、Ko君からブログにコメントがあった。彼の言うとおり、たしかに僕は一ヶ月たった今も、いまだに「亡くなった弟はどこに行ったのか?」という、考えても仕方の無いことを考え続けているような気がする。以前の僕だったら、まちがいなく非科学的だと斥けてしまっているし、今の自分の何割かも思っている。しかし、残りの何割かは、「どこかにいてもらわないと困る」と考えているわけだ。
病気の発覚からわずか一ヶ月弱で逝ってしまったことや、まだ若かったことが、そのような考えを持たせる原因になっているのだと思う。祖父母の死であれ、叔父の死であれ、あるいはその他の知り合いの死であれ、その人の魂がどこに行くのかは、常に考えさせられる問題なのだが、日常隠蔽されているこの疑問に対する執着の程度は、今回格別に高いのである。
僕と弟との最後のやりとりは、きわめてカジュアルに、MSNメッセンジャーで行われている。その中で彼は、「まあ死ぬことはないでしょ。」と楽観的な見通
しを書いている。その後虎ノ門病院に入院して頭痛がひどくなり始め、もう少し気持ちもシリアスになっていったのかもしれないが、それでもやはり、この戦い
が死に至る恐れを秘めたものではないという認識を持っていたようだ(そのような認識をもたらした医師の言葉の重みをどのようにとらえたらいいのか、僕には
いまだに答えがでない)。その後僕が対面したときの弟は、すでに自らの意思を表明することができない状態に陥っていて、そのまま死を迎えることになった。
彼が死ぬことになると知っていたとすれば、その前にいろいろ悔やんだり、言い残したりしたいことがあるはずで、それを意思として持つタイミングを一切持つ
ことができなかったというのは、僕にはとても耐えられないことだ(きっと事故などで突然亡くなる人のほとんどが、そういう境遇で亡くなっているのだろうけ
ど)。
僕らはその後の病気との戦いに寄り添い、最後に肉体の活動をやめるに至るプロセスに、(少なくとも僕は)彼の意思を見出している。このとき僕は、脳死に
至っているであろう彼の肉体ではなく、それとは別に存在する彼の魂の存在を仮定し、彼が肉体の活動を止めることを選択したと想像するのだけれど、しかしそ
の僕の想像力を引き出したものもまた、目の前にあった彼の肉体の存在だったのかもしれないとも思う。火葬が終わり、肉体が滅んでしまった今、その「存在し
てもらわないと困る」魂の行き先を、僕は何のよすがもないまま、考え続けざるを得ないのである。そしてそこがまさに、「殯の森」に出てくる、認知症の主人
公が墓の前でとる行動に、僕が共感する点だ。
もう一つのポイントは、弟の頭の中にあったものの行方である。これも当たり前といえば当たり前なのだけれど。彼の書いたもの、しゃべったもの、読んでいた
もの、見ていたもの、聞いていたもの、気に入っていたもの、などなど、外形的に、あるいは記憶として、彼が残していったものを、僕は改めて、少しずつた
どっていっている。そうするとたとえば、彼がキリスト教について思っていたこととか、国際化について思っていたこととか、MSNについて思っていたことと
か、いろいろなものについて、気がつくことになる。しかし外形的に残したものは、実はあまり多くない。彼がゆっくり何かを書き残す時間はそんなになかった
し、仕事の中で考えていたことだって、守秘義務と抵触することは書き残せていないだろう。以前のエントリーで、僕が彼から受け取ったものを大事に生きていこ
うと考えていると書いたけれども、実はそういうわけで、かなりの部分がすでに原理的に継承することの不可能な状態にあるのだ。アウトプットとして残されな
かったものは、もちろん口伝として残っていくこともあるけれども、彼の脳内で展開されていたもののうち、何か価値のあるものがあったのだとしても、もうそ
れはすでに消えてしまっている。思い出は断片的だ。記憶も断片的だ。いや、多くの作品を残す大作家の頭の中身だって、実はすべてアウトプットに体現されて
いるわけではない。そういうわけで、才能があろうとなかろうと、僕らの頭の中に去来するものすべては、記録されない限り、はかなく消えていくのである。で
も、弟が32歳2ヶ月で頭の中に蓄積していたものが、はかなく消えずにどこかに残っていて、いつかまた、それを発展させていくことができるようにしてあげ
たいと、願わずにはいられない。
————————-
以上が白浜に向かう電車で書いていたもの。その後白浜の宴会で、(職場も変わったし)「これからはもっと書いてください。」とO先生に励ましをいただい
た。たしかに、僕の脳内にあるつたない考えを、そのままためておいても、発展はしないし、はかなく消えていくだけだなと、自覚を新たにした。