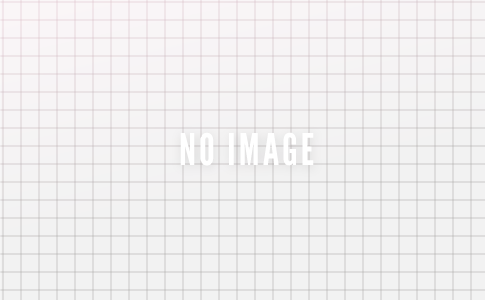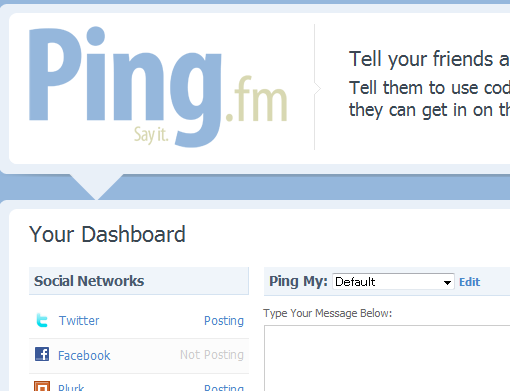Googleの「最高文化責任者」(Chief Culture Officer)であるStacy Savides Sullivan氏のインタビュー。Googleが独自のフラットな組織を維持するために、相当なエネルギーを注いでいることがよくわかる。
リンク: グーグル文化の担い手S・サリバン氏の仕事 – CNET Japan.
われわれは雇用プロセスに非常に重点を置いています。面接をするとき、まずはその人物が研究活動や学位に加えてバックグラウンドの観点から仕事をするのに
十分なスキルと経験を持っていることを見極めようとしますが、同時にその人物がよい文化を作り、チームに合うかどうかも見ていきます。(中略)
わたしが知る限り標準的な質問というのはありませんが、例えばですが、「飛行機にいくつのパン箱を詰めこむことが出来ると思いますか」というような質問を
するかもしれません。この質問は、その人物に適応力や柔軟性があるかをはっきり示してはくれませんが、確実に考えのプロセスや理由付け、その人物が正しい
答えなりなんなりを合理的に説明する筋道を示してくれるでしょう。これには明らかに正しい答えはありません。単に、その人の考え方や、考え方の手順につい
て知ろうとしているだけです。
これは人事採用に関する話であるが、学風によって成り立つ大学にとっても考えさせられる話題である。大学は教職員だけではなく、というよりもむしろ、入ってくる学生によって大きく雰囲気が変わる。もちろん大学が学問を行う場所である以上、高校までの学力が、その雰囲気を決める上で、大きくものをいうのはいうまでもない。
しかしそれだけではない。どんな学風の下に、どんな学生を育てて、どんな風に社会に送り出すのか。そういうトータルな発想に立つならば、それなりに練られたアドミッションポリシーのもと、学生を選抜することはできるのではあるまいか。もちろんこれだけ大学をめぐる状況が厳しくなってくれば、そんな厳しい選抜を行えないところも増えてくるだろう。でもそのためにポリシーを捨ててしまえば、あとは落ちていくのみだ。AO入試というのは、どんどん全入時代の学力不問の象徴のように見られるようになっている。AO入試でどんな質問をし、どのように多角的に学生の才能を見るのかという点について、どれだけの大学が、その評価法に工夫を凝らしているだろうか。
結局Googleにはたくさんの優秀な人材が応募してくるので、その中から自分たちの文化に合った人たちを選別していくことができるわけだが、そういう恵まれた環境に無い場合であっても、どこまで粘り強く、自分たちの文化に合った人を選び抜くか。またその「文化」なるものが、人々の十分評価されるものなのか。常に客観的な目を曇らせないようにしたい。