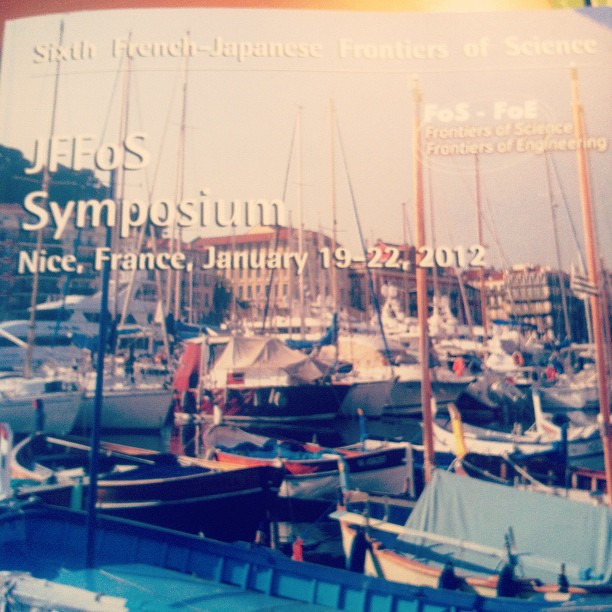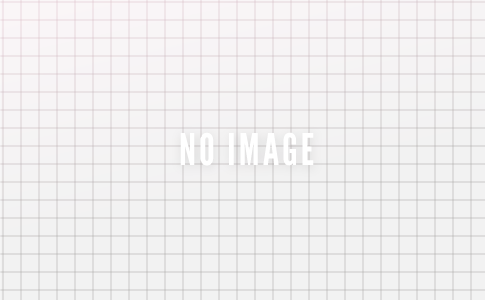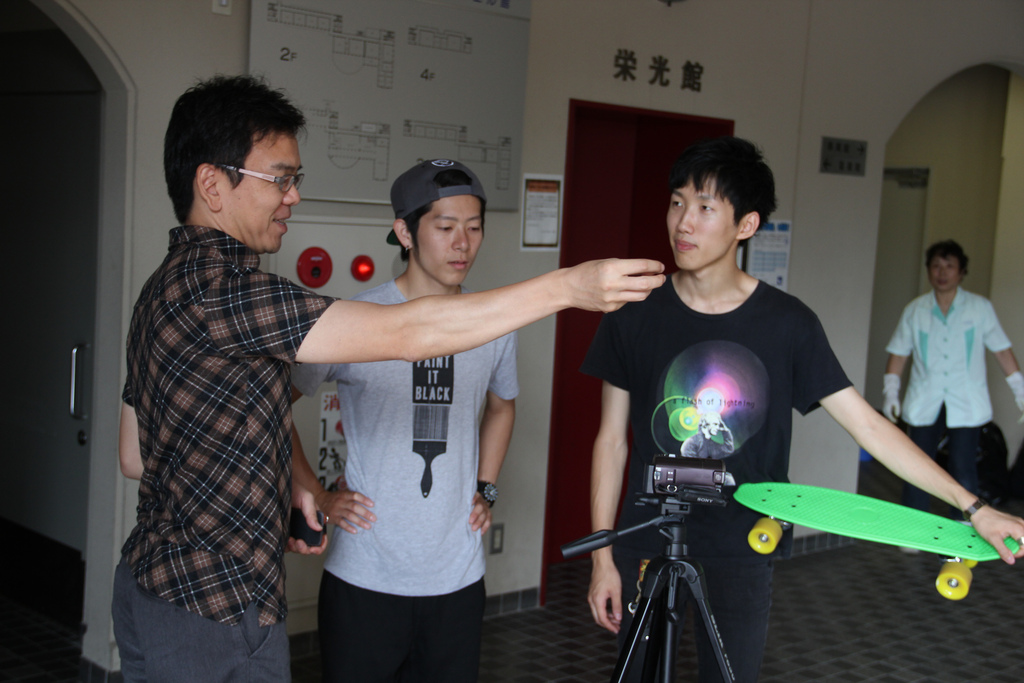「リベラルアーツ大学」である敬和学園大学で仕事をはじめて、5年が過ぎた。いつのまにか入試広報の仕事を任されて数年がたつ。地方の「実学志向」の中で、「リベラルアーツ」の学校が学生やその父兄にアピールするのは大変なこと。自分自身は「実学志向」に近いところにいる人間なので、仕事の中で「リベラルアーツ」をアピールする作業(さらにそれによって成果を出す作業)は、正直かなり骨が折れる。「リベラルアーツ」という言葉は、わかっているつもりでも、説得力のある説明が、なかなかできないのだ。
以下は3月24日に行われた、立教大学大学院の学位授与式における、吉岡知哉総長の言葉。「考える」技法を習得するための訓練体系である「リベラルアーツ」を、立教大学はなぜ重視しているのか。非常に説得力ある説明をされている。
卒業生の皆さんへ(2011年度大学院学位授与式) | 立教大学
では、大学の存在根拠とはなにか。
一言で言えばそれは、「考えること」ではないかと思います。
大学とは考えるところである。もう少し丁寧に言うと、人間社会が大学の存在を認めてきたのは、大学が物事を徹底的に考えるところであるからだと思うのです。だからこそ、大学での学びについて、単なる知識の獲得ではなく、考え方、思考法を身につけることが大切だ、と言われ続けてきたのでしょう。現実の社会は、歴史や伝統、あるいはそのときどきの必要や利益によって組み立てられています。日常を生きていく時に、日常世界の諸要素や社会の構造について、各自が深く考えることはありません。考えなくても十分生きていくことができるからです。あるいは、日常性というものをその根拠にまで立ち戻って考えてしまうと、日常が日常ではなくなってしまうからだ、と言ったほうがよいかもしれません。
しかし、マックス・ウェーバーが指摘したように、社会的な諸制度は次第に硬直化し自己目的化していきます。人間社会が健全に機能し存続するためには、既存の価値や疑われることのない諸前提を根本から考え直し、社会を再度価値づけし直す機会を持つ必要があります。大学は、そのために人間社会が自らの中に埋め込んだ、自らとは異質な制度だと言うことができるのではないでしょうか。大学はあらゆる前提を疑い、知力の及ぶ限り考える、ということにおいて、人間社会からその存在を認知されてきたのです。
既存の価値や思考方法自体を疑い、それを変え、時には壊していくことが「考える」ということであるならば、考えるためには既存の価値や思考方法に拘束されていてはならない。つまり、大学が自由であり得たのは、「考える」という営みのためには自由がなければならないことをだれもが認めていたからに他ならない。大学の自由とは「考える自由」のことなのです。
言葉を換えると、大学¥は社会から「考える」という人間の営みを「信託」されているということになると思います。
「スキル」や「技術」に特化した「実学志向」は、大学に「考える」という社会的役割が、もはや期待されなくなってしまったことの表れではないか。この点を、以下の通り強く危惧しているように思う。
しかしさらに考えてみると、大学への不信はもっと以前から存在していたのではないかと思われます。ある時期から、もはや大学には「考える」という役割が期待されなくなったのではないか。
社会が大学に求めるものが、「考える」ことよりもすぐに役立つスキルや技術に特化してきたことはそれを示しているのではないでしょうか。大学について語る場合の語彙も、「人材」、「質保証」、「PDCAサイクル」など、もっぱら社会工学的な概念に変わってきています。
近年、大学の危機が論じられることが多くなりましたが、その際問題になるのは、「グローバル化」と「ユニバーサル化」です。しかし、人間社会が大学に、考える場所であることを期待しなくなっているのであれば、そのことのほうがずっと深刻な危機ではないでしょうか。
このお話は、大学院生を前に話されている。学部生の卒業式では、少し違う内容でお話しされたようだ。
社会が揺らぐ中にあって、それぞれの大学が自ら存続しつつも、あるいは存続するために、特徴を出そうと躍起になっている。その中で「考える自由」、あるいは大学の自由をどのようにとらえるか。さらにはその自由をどのように学生に享受させ、一人一人の未来につなげていくのか。吉岡総長の言葉が、この時代の波をせき止めるパワーを持つのか、それは正直未知数だが、少なくとも「反時代的・反社会的な」発言としては、非常に大きな力を持っているように感じた。